「まにわくに投資した人の評判や口コミは?」
「サービスの利用を検討しているけど実際どうなの?」
まにわくは、1口10万円から不動産投資を始められる不動産クラウドファンディングサービスです。
実際に投資した人の評判や口コミを参考にしてサービスを利用するかどうかを判断したい、という方も多いのではないでしょうか。
まにわくに投資している人のリアルな声や投資するメリット・デメリットについて、詳しく紹介します。

日々不動産クラウドファンディングのファンド情報を調査し、Fund Bridgeへの掲載を実施しています。これまで、不動産クラウドファンディングに関する50以上のサービスを紹介してきました。不動産クラウドファンディングへの投資を検討している投資家の方に向けて、公平な立場でわかりやすい紹介を心がけています。
年商535億円の親会社エムトラストが運営し、平均利回りが10%を超えている不動産クラウドファンディング「TORCHES(トーチーズ)」が話題を呼んでいます。
そんなトーチーズですが、3月1日まで限定の出資キャンペーンを実施しています

キャンペーン詳細は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| キャンペーン名 | 投資応援キャンペーン |
| 実施期間 | 2025年12月10日〜2026年3月1日 |
| 内容 | 対象期間中に初回投資を完了した人にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼント |
| 発送タイミング | 条件達成から約1ヶ月以内に送付 |
| 注意点 | キャンペーンは予告なく終了する可能性あり/Amazonへの直接問い合わせは不可 |
出資完了が対象ではあるので、1万円であっても投資できればプレゼントの対象になります。
2月13日12時から募集される「目黒区鷹番3丁目ファンド」は、1万円から出資ができる内容になっています。

その他のファンドは10万円からの出資のケースが多いので、キャンペーンに少額から申し込んでみたい方は今のうちに投資家登録を済ませておくことをおすすめします。
より詳細を知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
まにわくの評判・口コミは?実際に投資している人の声を紹介!
X(旧Twitter)をリサーチした結果、まにわくの評判や口コミを発見したので紹介します。
まにわくの良い評判・口コミ
まにわくの良い評判と口コミは、以下の通りです。
まにわく27号,投資しました!
— Yusuke (@yus_life) July 3, 2025
ようやく週の後半😌
まにわく投資しました😉
— シルフィード (@HVkw8cpi9b64771) June 15, 2025
終了早かったですね~
まにわくから22号早期運用終了メール。メール見落としてたけど先月19号も早期運用終了してました。運用終了日は違うけどどちらも6月13日償還日。ちゃんと早期運用終了がある運営は安心できます😄キャピタル案件結構組成しているのに全く早期運用終了がない運営も投資中のところにあるんだよなあ🤔 pic.twitter.com/ETEaFReVGN
— だしかり (@SdwJz) June 6, 2025
まにわくの応募に間に合い投資できた、という声がみられました。
また、「早期運用終了がある運営は安心できる」といった好意的な声が上がっています。
まにわくの悪い評判・口コミ
まにわくの悪い評判と口コミは、以下の通りです。
まにわく17号落選〜😇
— ポイント@平凡サラリーマン (@pointpoint9999) November 17, 2024
倍率200%超えてる時点でヤバい気がしてたけど…🙄
とりあえずBATSUNAGUの抽選に申込ー
ここも倍率200%ぐらいになりそうだから落ちるかな?😅
まにわく落選‼️
— 毛布𝕏 (@hataraki_rev) September 15, 2024
当選した人がいる一方で、落選して投資できなかった、という声もありました。
まにわくのファンドには、募集金額を大きく上回る応募があるため、必ず投資できるとは限らないようです。
ファンドはどれも高倍率のため、投資家からの注目度の高さがうかがえます。
まにわくの強み・メリット5選
まにわくの強みとメリットは、以下の5つです。
- 平均利回り8%以上の高利回りファンドに投資できる
- 分配金を3ヶ月ごとに受け取ることができる
- 市況変動リスクを低減できる短期運用ファンドが中心
- 上振れて償還されるケースもある
- マスターリース契約により空室リスクを抑えられる
それぞれ解説します。
まにわくの強みとメリット1.平均利回り8%以上の高利回りファンドに投資できる
まにわくの直近10件の平均利回りは、7.81%です。(2025年7月時点)
一般的な不動産クラウドファンディングの利回りは約3~5%のため、まにわくの利回りの高さは強みだと言えます。
まにわくでは、一般的な不動産クラウドファンディングを上回る高利回りファンドに1口10万円から投資できるため、大きなリターンが見込めるでしょう。
まにわくの投資対象は、1都3県の築古物件が中心です。
築古一棟収益物件のリノベーションにより、付加価値をプラスすることで資産価値を向上させています。
長期的に安定した入居ニーズの確保と家賃・売却益の上昇が期待できるため、高い利回りでの提供が可能になります。
まにわくの強みとメリット2.分配金を3ヶ月ごとに受け取ることができる
まにわくの募集ファンドは、すべて分配サイクルが3ヶ月に設定されています。
3ヶ月ごとの短いスパンで分配金を受け取ることができるため、投資効果を実感しやすいでしょう。
また、分配金を再投資することで、資金を効率的に回せるため、資産の最大化を目指せます。
まにわくの強みとメリット3.市況変動リスクを低減できる短期運用ファンドが中心
まにわくは、3~12ヶ月の短期運用ファンドが中心です。
長期運用ファンドでは、運用中に急激な市況変動が発生した場合、不動産価値が低下し大きな損失を被る可能性があります。
一方で、短期運用ファンドの場合、短期間での急激な市況変動が発生する可能性は低めです。
そのため、長期運用ファンドと比較すると、短期運用ファンドでは、想定通りに運用できる可能性が高まるでしょう。
まにわくの強みとメリット4.上振れて償還されるケースもある
まにわくでは、想定利回りを上振れて償還されるケースもあります。
実際にまにわく7号ファンドでは、想定利回り7.5%を大きく上回る12%の利益が発生しました。
今後のファンドでも、利益が上振れる可能性もあるでしょう。
まにわくの強みとメリット5.マスターリース契約により空室リスクを抑えられる
まにわくのインカム型ファンドでは、不動産賃貸管理会社とマスターリース契約を締結しています。
インカム型ファンドとは、分配金のベースが賃料収入のファンドを指し、まにわくで今まで募集されたファンドは、すべてインカム型です。
マスターリースとは、第三者へ転貸することを目的とした一括賃貸借契約のことです。
マスターリース契約により、毎月の賃料が保証されるため、空室や家賃滞納が発生しても、安定した分配金が得られるでしょう。
まにわくの注意点・デメリット2選
まにわくの注意点とデメリットは、以下の2つです。
- 原則中途解約できない
- 倍率が高いため落選する可能性がある
それぞれ解説します。
まにわくの注意点とデメリット1.原則中途解約できない
一般的な不動産クラウドファンディングは、原則中途解約できません。
まにわくでも、一般的な不動産クラウドファンディングと同様、中途解約不可です。
ファンドの運用が始まると途中で現金化できないため、急に資金が必要になった場合に対応できないケースもあります。
そのため、不動産クラウドファンディングに投資する際には、当面使う予定がない余裕資金を充てることが重要です。
まにわくの注意点とデメリット2.倍率が高いため落選する可能性がある
まにわくは、毎回募集金額を大幅に上回る応募がある人気の不動産クラウドファンディングサービスです。
募集されるファンドは、どれも高倍率になるため、必ず投資できるとは限りません。
まにわく5号は、募集金額に対して1,114%の応募があった超高倍率ファンドでした。
何度も落選している投資家の声もあるため、他の不動産クラウドファンディングサービスと併用するなど工夫するとよいでしょう。
まにわくのリスク
一般的な不動産クラウドファンディングには、元本保証がありません。
まにわくも一般的な不動産クラウドファンディングと同様、元本割れする可能性があります。
まにわくでは、優先劣後システムやマスターリース契約など、リスクを低減する仕組みが採用されていますが、元本割れリスクを完全に排除することはできません。
そのため、不動産クラウドファンディングを利用する際には、元本割れリスクがあることを十分理解した上で、投資を判断することが重要です。
まにわくは儲かる?実績を確認
まにわくの募集ファンド累計は、27件です。
27件のうち、21件がすでに運用終了しています。
運用終了したファンド21件すべてが無事償還されており、利益の上振れが発生したファンドが1件ありました。
まにわくでは、元本割れなしですべてのファンドが無事償還されている実績があり、今後も利益の上振れが期待できることから、儲かる可能性は高いと言えるでしょう。
まにわくの仕組みをわかりやすく解説
まにわくは、1口10万円から不動産投資を始められる不動産クラウドファンディングサービスです。
不動産クラウドファンディングでは、インターネットを経由して不特定多数の投資家から出資を募り、集めた出資金をもとに事象者が不動産を購入・運用します。
不動産の運用で得られた賃料収入や売却益を、出資額に応じて投資家に分配する仕組みです。
まにわくは優先劣後システムを導入
まにわくでは、優先劣後システムを導入しています。
優先劣後システムとは、優先出資者である投資家が利益を優先して受け取れる一方で、劣後出資者である事業者が先に損失を負担するシステムです。
劣後出資以内の損失であれば、投資家が損失を被ることはないため、元本の安全性が高められるでしょう。
一般的な不動産クラウドファンディングの劣後出資割合は、10~30%程度です。
まにわくの劣後出資割合は、ファンドによって異なりますが、10~50%で設定されています。
一般的な不動産クラウドファンディングと同程度もしくは、それ以上の安全性が確保されています。
まにわくに税金はかかる?
まにわくの分配金には、税金がかかります。
まにわくの分配金は、雑所得として総合課税の対象です。
分配金から所得税と復興特別所得税の20.42%が、源泉徴収されます。
まにわくは確定申告が必要な場合がある
まにわくは、確定申告が必要な場合があります。
雑所得の年間合計が20万円以上の人や年収2,000万円以上の会社員など、一定の要件に該当する人は確定申告が必要です。
確定申告の要否は個別に判断されるため、税理士や所管の税務署に相談するとよいでしょう。
まにわくは「元本割れリスクを抑えながら利益の上振れが期待できる高利回りファンドに投資したい人」におすすめ!
まにわくは、元本割れリスクを抑えながら利益の上振れが期待できる高利回りファンドに投資したい人におすすめの不動産クラウドファンディングです。
まにわくでは、優先劣後システムやマスターリース契約により、元本の安全性が高められています。
市況変動の影響を受けにくい短期運用ファンドが中心のため、想定通りの利益が得られる可能性が高いでしょう。
まにわくでは、元本割れリスクを抑えながら想定利回り8%以上の高利回りファンドに、1口10万円から投資できます。
まにわくの運営会社情報
まにわくの運営会社は、株式会社新日本コンサルティングです。
株式会社新日本コンサルティングは、不動産投資の総合コンサルティング事業を展開する企業です。
株式会社新日本コンサルティングの会社概要
株式会社新日本コンサルティングの会社概要は、以下の通りです。
| 会社名 | 株式会社新日本コンサルティング |
| 本社所在地 | 東京都中野区弥生町2-4-9 ツナシマ第三ビル5階 |
| 設立日 | 2005年7月21日 |
| 代表者 | 籾山 敦輝典 |
| 資本金 | 1億円 |
| 取得している免許 | 宅地建物取引業者免許:東京都知事(3)第94029号 住宅宿泊管理業者免許:国土交通大臣(01)第F01683号 賃貸住宅管理業者:国土交通大臣(1)第5995号 建設業許可番号:東京都知事許可(般-3)第152624号 不動産特定共同事業免許:東京都知事第141号 |
まとめ
今回紹介したまにわくについて、重要なポイントを5つにまとめました。
- 平均利回り8%以上の高利回りファンドに投資できる不動産クラウドファンディングサービス
- 上振れて償還されるケースもある
- マスターリース契約により空室リスクを抑えられる
- 優先劣後システムにより元本の安全性が高められている
- 元本割れリスクを抑えながら利益の上振れが期待できる高利回りファンドに投資したい人におすすめ
高いリターンが見込める不動産クラウドファンディングに興味がある方は、まにわくの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

日々不動産クラウドファンディングのファンド情報を調査し、Fund Bridgeへの掲載を実施しています。これまで、不動産クラウドファンディングに関する50以上のサービスを紹介してきました。不動産クラウドファンディングへの投資を検討している投資家の方に向けて、公平な立場でわかりやすい紹介を心がけています。
年商535億円の親会社エムトラストが運営し、平均利回りが10%を超えている不動産クラウドファンディング「TORCHES(トーチーズ)」が話題を呼んでいます。
そんなトーチーズですが、3月1日まで限定の出資キャンペーンを実施しています

キャンペーン詳細は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| キャンペーン名 | 投資応援キャンペーン |
| 実施期間 | 2025年12月10日〜2026年3月1日 |
| 内容 | 対象期間中に初回投資を完了した人にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼント |
| 発送タイミング | 条件達成から約1ヶ月以内に送付 |
| 注意点 | キャンペーンは予告なく終了する可能性あり/Amazonへの直接問い合わせは不可 |
出資完了が対象ではあるので、1万円であっても投資できればプレゼントの対象になります。
2月13日12時から募集される「目黒区鷹番3丁目ファンド」は、1万円から出資ができる内容になっています。

その他のファンドは10万円からの出資のケースが多いので、キャンペーンに少額から申し込んでみたい方は今のうちに投資家登録を済ませておくことをおすすめします。
より詳細を知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
本サイトのコンテンツは事業者の公式サイトから抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

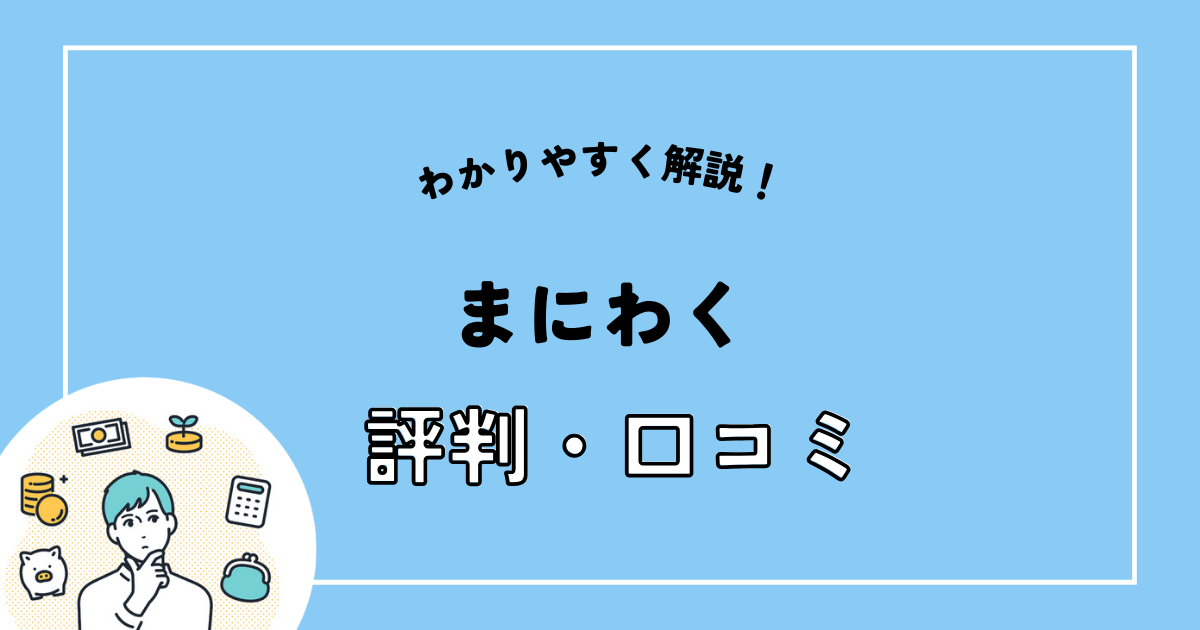
コメント